営業形態

1.介護保険タクシー
元来、介護タクシーと言えばこのサービスを指していました。介護保険が利用できるタクシーで、介護保険指定業者番号を取得した業者が提供できるサービスです。
要介護1以上でケアマネが作成するケアプランに沿って提供されます。介助から送迎までワンストップでの提供も可能です。
一方、利用用途が限られ家族の同乗ができない。通院や役所限定。いつでも電話で呼べるサービスでない。等、保険制度による制約事項が多いサービスです。
施設入居者や在宅でも介護サービスを多用している場合は点数が足りず使えない。等、サービスの性質や事業者の少なさから提供機会が少なく、
現在では、自費タクシーを介護タクシーと呼ぶのが一般的になっています。
2.介護タクシー
介護保険事業を併設しない業者が行うタクシーで、福祉タクシーとも言われます。保険適用外ですので、介助料に介護保険は使えません。運賃は
一般タクシーと同じ距離時間併用か時間制です。反面、保険制度を利用しないサービスですので、制度上の縛りがなく、融通が利くのがメリットです。
サービスを提供する為には、ドライバーは二種免許といずれかの介護資格を取得し、旅客運送事業の認可と緑ナンバーを取得する必要があります。
3.その他
福祉有償運送と呼ばれる移送サービスもあります。福祉タクシーと混同されがちです。NPOや市町村、社会福祉法人や医療法人などが運営するもので、
営利を目的とせず、利用者は予め登録されている必要があります。ドライバーは必ずしも介護資格保有者、二種免許保持である必要はなく、
社会福祉協議会等が主催する福祉有償運送運転者講習、セダン等運転者講習を受講する事でサービス提供が可能になります。
介助は乗降のみ。車両は白ナンバーでも運行できます。
Webサイト等で「介護タクシー」として、一緒くたに表記、説明されていますが、それぞれで性格が異なります。
当社は2.に属します。保険タクシーと福祉運送の不便、不足分をカバー出来るのが介護タクシーです。
メリットとデメリット
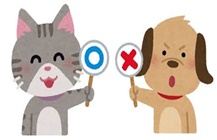
○メリット
車イス利用の方であれば、そのまま乗車できます。また、ドライバーが介護資格を保有してい
ますので、移乗や介助の直接的なサポートが可能です。出先における身の回りのお世話も心配ありません。
×デメリット
後述しますが、運賃以外の費用が発生します。小規模、個人事業者も多い為、送迎が重なった場合、予約が取れなかったり、お待ち頂く場合があります。
車両区分

使われる車両の区分は、地域により多少の違いはありますが、
京浜地区では、普通、大型、特大の3区分に分かれています。
1.普通車
軽自動車から2000CCクラスの車が含まれ乗車定員が6名まで。運賃は初乗り迎車690円から730円、加算運賃が310Mから293Mで各社設定しています。
2.大型車
2000CCを超えるクラスの車両で乗車定員が6名まで。運賃は初乗り迎車720円から770円、加算運賃が297Mから263Mで各社設定しています。
3.特定大型車
乗車定員が7名以上の車両。運賃は初乗り迎車760円から810円、加算運賃が266Mから239Mで各社設定しています。



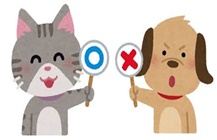

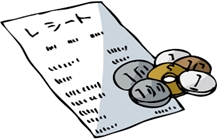 1.介助料(ケアチャージ)
1.介助料(ケアチャージ) 「病院手配の介護タクシーで、高速を使い30Km先の病院へ転院。リクライニングをレンタル。費用は3万弱。
後日、別業者で戻りの送迎を行なった所、掛かった費用は1.5万。」倍近い開きです。
「病院手配の介護タクシーで、高速を使い30Km先の病院へ転院。リクライニングをレンタル。費用は3万弱。
後日、別業者で戻りの送迎を行なった所、掛かった費用は1.5万。」倍近い開きです。
 JPNタクシー:新しくなった一般タクシーです。車イス乗降可能ですが、
横から乗降する構造で、準備にも時間が掛かります。
JPNタクシー:新しくなった一般タクシーです。車イス乗降可能ですが、
横から乗降する構造で、準備にも時間が掛かります。 UDタクシー:スロープ乗降ができる設計で、一般のタクシー会社でも導入されていますが、
当日受け付けが多く、保有台数が少ない。など、なかなか予約が取れないようです。
UDタクシー:スロープ乗降ができる設計で、一般のタクシー会社でも導入されていますが、
当日受け付けが多く、保有台数が少ない。など、なかなか予約が取れないようです。